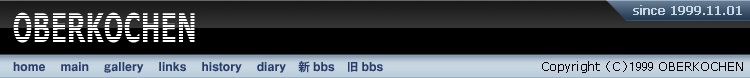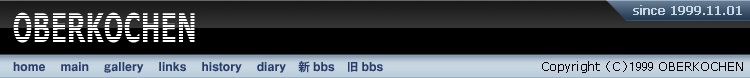|
PART 11 「黒猫館」
物語:
昭和16年初冬、信州のかたすみにおいて…。
帝都の学生、村上正樹が目にしたその書生募集の新聞広告には、なにか不思議な匂いがあった。三千円という並外れた給金、人里離れた屋敷での書生生活。日に日に強まる統制色と無縁の空気を感じ取った村上は、この求人に応募することを決意する。
館までの途上、利用した営業車の運転手は、鮎川邸のことを皆、畏れとともに“黒猫館”と呼ぶ旨、話していたが、村上にはそれがなにを意味するのか感じ取ることはできなかった。
ほどなく、“黒猫館”へと到着した村上はそこで鮎川家の娘、亜理沙とメイドの少女あやに出迎えられた。
あやの案内で応接間へと通された村上は館のあるじ、冴子と出逢う。彼女は妖艶な雰囲気を持つ美しい女性だった。
冴子は男たちが戦争へと駆り出されていくことに心を痛め、書生を募ったのだという。3ヶ月前、夫に先立たれたためか、彼女の瞳には愁いがあった…。そして、その夜が冴子と村上にとって、初の逢瀬となった。
しかし、村上にはそのようすがだれかに覗かれていると感じられてならなかった。それだけではない。“黒猫館”にはラジオ、新聞、電話すらないのだ。とらえどころのない訝しさを覚えながらも、村上は冴子との関係を深めていく…。
未亡人に供されるまま、ワインを口にした村上のもとへ、あやが呼び出されてきた。冴子は彼女に服を脱ぐよう命じる。驚く村上に対して、冴子はこともなげに「主人が生きておりましたころは、よく三人で愛し合ったものです」と言い放つのであった。
ふたりの女とひとりの男による饗宴がはじまった。そのさなか、再びつぶらな瞳が扉の影から宴のようすをうかがう。物音に気づいた冴子がドアを開けたところ、そこには自慰に耽る亜理沙の姿があった。
そして…めくるめき時が流れる。村上にはこの宴が終わりなく続くように思われた。それになんだか体が重く感じられる。部屋で休んでいたところ、あやが扉越しに話しかけてきた。
それは実に衝撃的な内容であった。村上の飲んでいたワインには媚薬が入れられており、そこには快楽と隣合わせの死がひそんでいるとのこと。館の当主もそのため、死に追いやられたと、あやは告げた。村上は愕然としながらも、最後の力をふりしぼって、“黒猫館”を脱出した。
数ヶ月後、大学の一室でうたた寝をしていた村上のもとへ友人が新聞を持って現れた。かれは日本軍による真珠湾攻撃のニュースを伝えに来たのだが、村上にはその記事の下に小さく載っていた「山奥の西洋館、全焼す」の見出しがとても気にかかった。
それはまぎれもなく、“黒猫館”のことだったからである。これにより、村上はあの出来事が夢や幻ではなかったと確信するに至った。 記事は住人を行方不明と報じていた。ならば、彼女たちが生きている可能性もある。再び出逢う機会も巡ってくるかもしれない。召集を間近に控えて、村上は“黒猫館”におけるたおやかな日々にふと想いをはせた。
スタッフ:
キャラデザイン/ストーリー原案/コンテ/原画/作画監督:富本たつや
キャスト:(声優)
村上正樹: 目黒裕一
鮎川冴子: 鳳芳野
鮎川亜理沙: 安藤ありさ
あや: 溝口あや
BGM :
・黒猫館のテーマ
J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ
第1番 ト短調 BWV.1001
第1楽章「アダージョ」
J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ
第2番 ニ短調 BWV.1004
第5楽章「シャコンヌ」
・亜理沙のセレナーデ
J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ
第3番 ホ長調 BWV.1006
第3楽章「ガヴォット・アン・ロンド」
・蓄音機が奏でる音楽
およびエンディングテーマ
アルカンジェロ・コレッリ
「ラ・フォリア」 ト短調 作品5の12
・ラストの回想シーン
タルティーニ/クライスラー
「コレッリの主題による変奏曲」
作品解説:
富本たつや氏の作品群のなかにおいても、ひときわ評価の高い名作、それが黒猫館である。現代劇もしくは異世界ものが多いくりいむレモンにおいて、戦前の日本を舞台としている点がまず新しい。そして、当時のモダニズムを忠実に再現した考証の確かさ。
従来、きわものとしての扱いしかされなかったアダルトアニメを、真の意味で大人の鑑賞に堪えうる作品へと昇華させたのは、富本氏の豊かな表現力によるところが大きかった。
くりいむレモンが当時あれほどのヒットをとばしたのは、マーケティング戦略が優れていたわけではない。むしろ、おりからのロリコンブームに便乗するようなかたちで、泥縄式にはじめられたとみるほうが自然である。にもかかわらず、ふたを開ければ大ヒットをよぶ。これをどう解釈すべきか。
映像作品(とりわけ、アニメーション)を成功へと導く鍵はキャラクターにある。魅力的なキャラを創り出せるか否かによって、作品そのものの命脈までも決せられてしまうのだから、作り手の責任は重大である。
表層のみが整っていたとしても、キャラクターは起たない。その見せ方を極めなければ、真に受け容れられはしないのである。その意味において、富本氏の力量はやはり傑出していた。
黒猫館を鑑賞した者であれば、だれしもが感じるであろう冴子の妖艶さ、あやの可憐さ、亜理沙の愛くるしさ。それらは富本氏が生命を吹きこんだ結果、生まれたものであった。25分(実質は20分)という短いランニングタイムのなかで、キャラクターを起たせ、ストーリーを紡ぐ。初期のくりいむレモンの成功は、富本氏の才能なくしてありえなかった。
物語は黒猫館の炎上という、その後の日本の行く末を暗示させるようなフィナーレで結ばれているが、実のところ、このあとには続編の構想もあった。富本氏の話では、黒猫館の真の続編は舞台を上海へと移したのち、大日本帝国の興亡と歩を合わせるようなかたちで展開し、退廃のなか滅びゆくものたちの運命を無常の旋律とともに描き出す予定だったという。
だが、創映側のコマーシャリズムに疑問を抱いていた富本氏は、この黒猫館を最後にメインスタッフから降板する。そして「くりいむレモンPART14
なりすスクランブル」のコンテをもって、くりいむレモンの制作自体にも関わらなくなってしまう。その結果、一番の割を食ったのはファンであった。今後、アニメ以外のかたちででも、先の企画が日の目を見ることはあるのだろうか。
寸刻のうちに価値観が変わりゆくこの時代に、いまなお輝きを失わぬ名作、黒猫館。あなたなら、鑑賞後、どのような感慨をいだくであろうか。
|